香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
〒760-0029 香川県高松市丸亀町13番地3 丸亀町参番街東館6F
再開発で全国的に有名な高松丸亀町商店街のほぼ中心にあります
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
087-823-7755
相続税の試算と納税資金・分割資金の捻出

まずは、相続税の試算が必要で、相続が発生した場合の相続税額を知っておく必要があります。それも農業を継承する相続人がいるかいないかで、相続税は大きく変わってきます。「農業相続人が農地等を相続した場合の納税猶予の特例」(以下「納税猶予」)をうけるか否かで相続税が大きく異なります。
納税猶予される税額も農地の全てで受けるのか、一部分で受けるのかによっても違ってきます。手元にある現金預金で支払えればいいのですが、不足する金額があれば認識する必要があります。
現金預金で相続税の納付が困難な場合、相続税の延納(最長20年)や物納も選択することも可能ですが、それらが無理なときには、農地以外の土地または農地の一部を売却しなくてはなりません。また、納税資金以外にも農業相続人以外の相続人に分ける財産として、資金が必要となる場合があります。それらも合わせた資金を用意するにはどこをどれだけ処分しなければならないのかを考えておく必要があります。
処分土地の選定と土地評価

通常は相続人のなかで、農業相続人は1人になることが多いので、農業相続人以外の相続人に分ける財産をどうするかを検討しておく必要があります。
「農業相続人以外の相続人に分ける土地はあるのか」「金銭で分割を求める相続人のために、売却する土地はどうするのか」を事前に考えておいて下さい。
土地を売却するには、土地の測量と土地境界の確定等の作業が必要で、思わぬ時間がかかることがありますので、早目の対応が絶対に必要です。
相続対策にはいろいろありますが、一般的には農家は母屋を含め、広い土地を保有しているため、土地の相続税評価を下げる対策が可能かどうか検討します。農地・母屋・その他の土地について、土地の利用状況や賃貸形態を変更することによって、広大地評価が可能になります。もともと広い土地なので、評価の単価を下げられれば、相続税評価に与える効果は大きくなります。
農地の納税猶予

農業を営んでいた被相続人から、相続人が農地を相続し、農業を継続する場合、農地の価額のうち、農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額については、その相続人が農業を継続している限り、その納税が猶予される制度です。この猶予されている税額のことを農地等納税猶予税額といいます。この農地等納税猶予税額は、特例の適用を受けた相続人が死亡した等、一定の要件に該当しない限りは納税が免除されません。
この特例を受けるためには、相続税の申告書に納税猶予内容を記載して、申告期限までに必要書類(適格者証明書、担保関係書類等)を添付して申告しなければなりません。相続人間で言い争いがあって、1人でもその農地の分割に反対する相続人がいて、相続税の申告期限までに納税猶予の申告ができない場合は、納税猶予そのものができなくなるので注意が必要です。
相続発生後の対策
被相続人に配偶者がいる場合には、配偶者に農業相続人になってもらい、配偶者が納税猶予を受け、2次相続時に再度、その子供である相続人が農業を継続していくかの選択をすることができます。
納税猶予を受けた配偶者が高齢で実際に1人でできない場合には、実質的には子供が農業を行い、配偶者が農業を継続することも可能です。
生産緑地の有効利用や売却
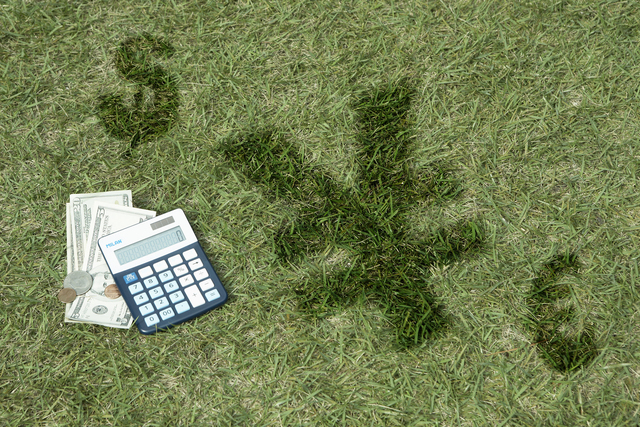
生産緑地の農地は、農地以外の利用が制限されており、建物の建築、造成ができず、売却等もできません。ただし、主たる従業者が死亡した場合には、生産緑地を解除して、賃貸建物を建てて有効利用することや、売却することもできます。ところが、生産緑地を解除するには、農業委員会への申請や市区町村長への申し出等の手続きが必要で、最低3ヵ月以上かかるため、余裕をもった計画が必要です。



