香川・高松で相続と不動産に強い税理士 (運営:池田達彦税理士事務所)
〒760-0029 香川県高松市丸亀町13番地3 丸亀町参番街東館6F
再開発で全国的に有名な高松丸亀町商店街のほぼ中心にあります
無料相談実施中
お気軽にお問合せください
お気軽にお問合せください
087-823-7755
遺言の作り方
民法では、遺言者の真意を確保し、争いを避けるため、法律に定める一定の方式の遺言でなければ無効であるとしています。
遺言には、次のように幾通りかの方式がありますが、このうち最もよく利用されているものは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
遺言の方式
(1)普通方式 ①自筆証書遺言
②公正証書遺言
③秘密証書遺言
(2)特別方式 ①危急時遺言(臨終遺言)
②隔絶地遺言
自筆証書遺言

遺言内容の全文と日付および署名を自書し、押印(実印でなくてもかまいません)して作成する最も簡便なものであり、遺言書の内容はもちろん、作成したことも秘密にしておくことができます。遺言書の書き方としては、平明な文章を判読しやすい文字で記すことが大切です。遺言書であることがわかる体裁が大切で代筆、テープレコーダー、パソコンやワープロによるもの、および日付印やゴム印等を利用したものは効力がありません。
遺言者が自分一人で作成できるという手軽さにその長所がある一方、隠匿、偽造、変造または破棄されるおそれがあるうえ、記載の誤り、書き落とし、あるいは保管場所の確保などの問題があり、さらには相続発生時に家庭裁判所における検認手続も必要となります。
文意の不明確等から、遺言内容の解釈をめぐる争いが起きないように注意することも大切です。遺言があることで、かえって争いを拡大するようでは意味がありません。
表題は、「遺言状」「遺書」「遺言」などと書いても差し支えありません。
また、封印のある遺言書は、相続人またはその代理人の立会いのもと、家庭裁判所において開封しなければなりません。
なお、遺言書の文字や字句を訂正したり、加除する場合には慎重な注意が必要です。具体的には、遺言者が訂正または加除した箇所を指示し、これを変更した旨を付記したうえ、特にこれに署名し、かつ、その変更の箇所に印を押さなければならないと決められています。
公正証書遺言

これは、公証人が作成した公正証書によって遺言するもので、公証人より筆記作成され、原本が公証役場に保存されるため、偽造や紛失のおそれはなく、検認手続も不要ですので、安全、確実な方法です。
なお、公正証書遺言には、必ず2人以上の証人の立会いが必要となります。この場合、未成年者ならびに推定相続人、受遺者等の利害関係人は、証人となることはできません。信頼できる友人、知人のほか、弁護士、または司法書士などが適任です。
公正証書遺言の作成手続きは、次のとおりです。
① 2人以上の証人の立会いのもとで
② 遺言者が遺言の内容を公証人に話します。言語障碍者、聴覚障碍者も、通訳人の通訳、筆談等により公正証書の作成ができます。
③ 公証人が遺言者の口授を筆記し、これを遺言者および証人に読み聞かせ、若しくは閲覧させます。
④ 遺言者および証人が筆記の内容の正確なことを承認したあと、各自これに署名、押印します。
⑤ この証書に、公証人が法律の規定により作成した旨を付記したうえ、署名、押印し、正本を遺言者に交付します。原本は、公証役場に保管されます。
なお、公正証書の作成に要する手数料は相続人等ごとに取得する財産の時価に応じて定められています。
また、遺言者が病気などの場合には、公証人に自宅や病院等へ出張してもらうこともできます。
秘密証書遺言
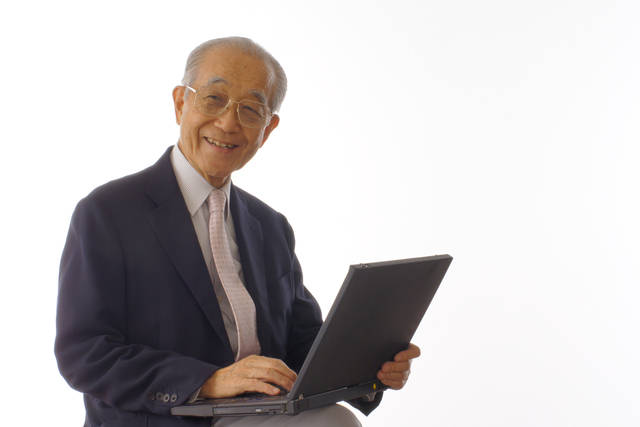
これは、遺言の内容を秘密にしておくために、遺言書の封入された封書を公証人の手で公証しておくもので、秘密性のない公正証書遺言の弱点と偽造・隠匿などのおそれのある自筆証書遺言の弱点を補うものです。遺言者が公証人と証人の前で述べた事実が公証人と証人の前で述べた事実が公証人によって公証され、遺言書の内容については公証されていないので、家庭裁判所の検認手続が必要となることや、紛失も懸念され、実際には、あまり使われていません。
この作成手続きは、次のとおりです。
① 遺言者は、遺言書を作成し、これに署名、押印し、封筒に入れ封印します。遺言書の全文、日付は、自筆証書遺言のように必ずしも自筆する必要はなく、代筆、ワープロやタイプによるものでもかまいません。
② 遺言者は、2人以上の証人の立会いのもとに公証人へ封書を提出します。
③ 公証人は、遺言書が提出された日の日付と遺言者の自己の遺言書である旨の申述を封紙に記載のうえ、遺言者および証人とともに署名、押印します。
危急時および隔絶地での特別方式による遺言

これは、死期の迫っている危急時に、自分で遺言書を書く体力も気力もないような場合の遺言(危急時遺言)や、伝染病などのための隔離施設、または船上といった隔絶地における遺言(隔絶地遺言)であり、異常な事態に対応する特別の方式といえます。
しかし、この遺言を行っても、事情が変わって前述の普通方式による遺言が可能となれば、可能となった日から6ヶ月を経過すると無効となります。
例えば、危急時遺言の作成手続きとしては、3人以上の証人の立会いのもとで、1人の証人が遺言者の口述している内容を筆記し、これを他の証人と遺言者に読み聞かせ、または閲覧させた上、各証人が署名、押印した後、20日以内に家庭裁判所に確認の手続をすることが必要です。





